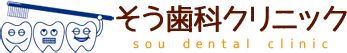こんな症状に心当たりは
ありませんか?
- ブラッシング時に歯茎から血が出る
- 朝起きた時、口の中がネバネバする
- 歯がぐらぐらと動く
- 歯と歯の間によく食べ物が詰まる
- 歯茎が赤く腫れている
- 口臭がする
- 以前よりも歯が長くなった気がする(歯茎が下がった)
- 硬いものがしっかりと噛めない
初期である歯肉炎は歯茎が炎症を起こしている状態です。歯を磨くと血がでたり、歯茎が赤く腫れたりブヨブヨしたりします。また、細菌が口内で増えると口の中が粘ついて不快に感じます。
症状が進行し歯周炎になると、膿が出て口臭の原因になったり、骨が溶けて歯がグラついたり抜けてしまい、最後には歯を失ってしまいます。
歯周病は口内だけでなく、身体の病気にも関係しています。歯周病菌や毒素が血液によって心臓や肺などの臓器に運ばれると、呼吸器疾患や心疾患などの全身疾患を引き起こす可能性があるので、異常を感じたらすぐに検診に行きましょう。
糖尿病の人はとくに要注意です。糖尿病を患っている人は歯周病にかかっている人が多いので、糖尿病だけど歯周病ではないという人は、一度検診に行ってみるといいでしょう。
症状が進行し歯周炎になると、膿が出て口臭の原因になったり、骨が溶けて歯がグラついたり抜けてしまい、最後には歯を失ってしまいます。
歯周病は口内だけでなく、身体の病気にも関係しています。歯周病菌や毒素が血液によって心臓や肺などの臓器に運ばれると、呼吸器疾患や心疾患などの全身疾患を引き起こす可能性があるので、異常を感じたらすぐに検診に行きましょう。
糖尿病の人はとくに要注意です。糖尿病を患っている人は歯周病にかかっている人が多いので、糖尿病だけど歯周病ではないという人は、一度検診に行ってみるといいでしょう。
歯周病は、口内の細菌が歯と歯茎の間に入り込んで繁殖し、炎症が起こる病気です。
歯肉だけが炎症を起こしている状態を「歯肉炎」、歯根や骨にまで広がっている状態を「歯周炎」といい、歯周炎まで進行してしまうと歯がグラついたり、食べ物が噛みにくくなったりして、最後は歯が抜け落ちてしまいます。
歯周病は痛みがなく、静かに進行していくので自覚症状がないことが多いです。歯茎の異常で気づいたときには、すでに歯周炎まで進行していることもあります。気づかないうちに症状が進行していくので、silent disease(サイレント病)とも言われます。
歯周病は歳を重ねてからの病気だと思われがちですが、日本人の約7割は歯周病です。年代も10代から60代以降という幅の広さです。歯を失う1番の原因である歯周病は、若い内から予防をしておかないと、どんどん症状が進行していき、最後に歯を失ってしまいます。
歯肉だけが炎症を起こしている状態を「歯肉炎」、歯根や骨にまで広がっている状態を「歯周炎」といい、歯周炎まで進行してしまうと歯がグラついたり、食べ物が噛みにくくなったりして、最後は歯が抜け落ちてしまいます。
歯周病は痛みがなく、静かに進行していくので自覚症状がないことが多いです。歯茎の異常で気づいたときには、すでに歯周炎まで進行していることもあります。気づかないうちに症状が進行していくので、silent disease(サイレント病)とも言われます。
歯周病は歳を重ねてからの病気だと思われがちですが、日本人の約7割は歯周病です。年代も10代から60代以降という幅の広さです。歯を失う1番の原因である歯周病は、若い内から予防をしておかないと、どんどん症状が進行していき、最後に歯を失ってしまいます。
-
歯周病は、歯と歯茎の間の間(歯周ポケット)に歯垢(プラーク)という細菌の固まりが溜まり、この細菌が繁殖して起こります。歯磨きすると血が出たり、歯肉が赤く腫れたりするのは、細菌の毒素で炎症を起こしているからです。
プラークは放置していると歯石になります。歯石は歯磨きでは除去できないため、歯医者で取り除いてもらうしかありません。プラークや歯石をそのままにしていると、歯周ポケットが深くなって細菌がさらに溜まり、歯周炎に進行してしまいます。 -
歯周病の原因はプラークですが、口内環境や生活習慣が乱れていても歯周病のリスクが高まります。
歯並びが悪いと、きちんと磨けていないところにプラークが溜まって炎症を起こします。虫歯を治療したときの被せ物が歯に合っていないと、やはりプラークが溜まりやすくなります。また、普段から甘いものを多く食べる習慣は歯周病菌を増殖させ、喫煙やストレスは歯周病菌への抵抗力を弱めます。
-

歯肉炎
初期段階の歯周病です。歯周ポケットの深さは3mm程度で、ブラッシング時に血が出るなどの症状が現れることがありますが、目立った自覚症状はありません。 -

軽度歯周炎
歯を支える組織や骨(歯槽骨)が溶け始めた状態です。歯周ポケットの深さは4mm程度で、歯茎が腫れたり、冷たいものがしみたりするようになります。 -

中等度歯周炎
歯槽骨が半分程度溶けた状態です。歯を指でさわるとぐらぐらと動くようになります。歯周ポケットの深さは6mm程度で、歯茎の腫れ、出血のほか、歯が浮いているように感じたり、口臭がきつくなったりするなどの症状が現れます。 -

重度歯周炎
歯槽骨がほとんど溶けてしまった状態です。歯周ポケットの深さは8mm程度で、歯茎が下がって歯が長く見えるようになったり、歯がぐらついたり、歯茎から膿が出たりするなどの症状が現れます。放置すると、歯が抜け落ちてしまうこともあります。
-
歯周病が進行すると、「歯周ポケット」と呼ばれる歯と歯茎の間の隙間が深くなります。
そのため、専用器具を使って歯周ポケットの深さを測定し、歯周病の進行度合いを確認します。 -
歯周病が進行すると、「歯槽骨」を呼ばれる歯を支える骨が溶けて、歯がぐらぐらと動くようになることがあります。
そのため、ピンセットのような器具で歯をつまんで動かして動揺度を測定し、歯周病の進行度合いを確認します。 -
レントゲンによって歯槽骨の状態などを検査し、歯周病の進行度合いを確認します。
歯周病に一番効果のある予防は、プラークを溜めないことです。プラークは糖分を餌に増殖するので、糖分のとりすぎに注意しましょう。朝晩の食後には忘れずに歯磨きを行い、歯と歯茎の間を意識して磨きます。昼食後は糸式ようじやデンタルフロスなどで食べ残しがないようにケアするだけで十分です。プラークに餌を与えないようにしましょう。
また、ドライマウスは歯周病菌の繁殖を増長します。唾液の分泌量が少ない人は、アメやガムを食べたり唾液腺のマッサージをしたりして唾液の分を促しましょう。
口内環境を整え、生活習慣を見直すことで、歯周病を予防することができます。
また、ドライマウスは歯周病菌の繁殖を増長します。唾液の分泌量が少ない人は、アメやガムを食べたり唾液腺のマッサージをしたりして唾液の分を促しましょう。
口内環境を整え、生活習慣を見直すことで、歯周病を予防することができます。
歯周病は、末期になると自然に歯が抜けてしまうという怖い病気です。歯周病によって失った歯茎や顎の骨は元に戻すことができないため、それ以上進行しないよう早めに対処することが大切です。
歯周病かも?と思ったら、加古川市の歯医者そう歯科クリニックにお越しください。患者さまができるだけ長くご自分の歯を保てるように、サポートさせていただきます。
歯周病かも?と思ったら、加古川市の歯医者そう歯科クリニックにお越しください。患者さまができるだけ長くご自分の歯を保てるように、サポートさせていただきます。